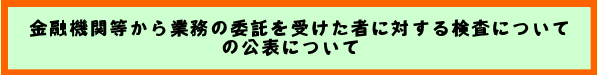| (1) |
調査対象
調査対象285社のうち、株式関連業務を行っていない63社を除く222社から報告を受けました。その内訳は、国内証券会社199社(うち、金融庁監理22社、財務局等監理177社)、外国証券会社23社でした。
また、リテール部門について報告のあった社が193社、ホールセール部門について報告のあった社が40社、自己売買部門について報告のあった社が222社でした。 |
| (2) |
誤発注の発生状況
平成17年1月〜12月の間に上記222社で発生した誤発注は14,318件。そのうち、売買代金1億円超の誤発注は667件、損失金額1億円超の誤発注は1件でした。 |
| |
| (注) |
全国証券取引所の平成17年の約定件数(現物株式)は概算で549百万件。これに対する誤発注発生率は100万分の26(0.0026%)となります。また、売買代金1億円超の誤発注発生率は100万分の1.2(0.00012%)とります。 |
|
| (3) |
株式等の売買発注業務の管理 |
| |
| (1) |
発注制限・警告の解除への管理者の関与の状況
発注制限・警告の解除について、管理者の関与なしで発注者自身が行うことができる社が見られました。この傾向は特にホールセール部門において顕著でした。 |
| (2) |
売買システムを統括するCIOなどの選任状況
売買システムを統括するCIO又はこれに準ずる者を選任していない社が222社中46社(21%)ありました。 |
| (3) |
株式売買発注業務に関する研修等の実施状況
売買発注業務担当者に対して株式売買発注業務に関する研修を実施していない社が222社中105社(47%)ありました。 |
|
| (4) |
発注システムの設計・管理状況
発注システムにおいて制限値の設定が不十分な社が見られました。具体的には、売買代金による制限が設定されていない社が222社中37社(17%)ありました。また、上場株式数を考慮した制限は、ほとんどの社で設定されていませんでした(222社中220社(99%))。 |
| (5) |
初値成立前の新規上場銘柄にかかる制限設定
初値成立前の新規上場銘柄について、公募価格等を基準とした制限が設定されていない社が222社中118社(53%)ありました。 |
| (6) |
大規模な誤発注に対する危機対応策の策定状況
全社において、誤発注が発生した場合の対応を定めたマニュアル等が策定されていましたが、昨年12月に発生したような大規模な誤発注が想定されていないことから、そのような場合における事実の開示方法を含め、対応策を定めている社はありませんでした。 |