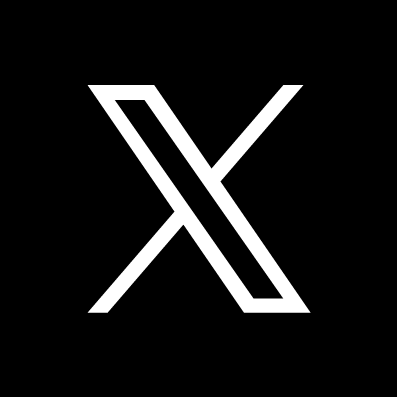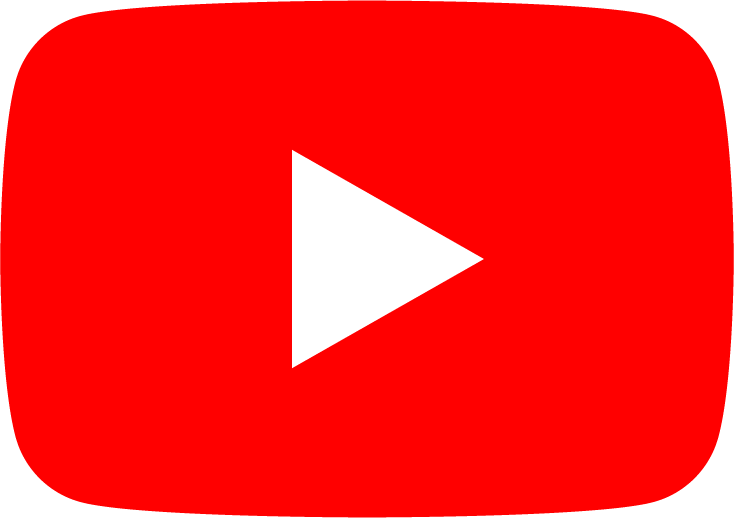- ホーム
- 国会提出法案等
- 国会提出法案
- 第156回国会における金融庁関連法律案
- 公認会計士法の一部を改正す…
公認会計士法の一部を改正する法律案要綱
証券市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査の充実及び強化を図るため、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供及び公認会計士の継続的監査の制限等公認会計士及び監査法人の独立性の強化、公認会計士及び監査法人に対する調査権の拡充並びに公認会計士審査会による監視制度の導入等監視監督機能の充実及び強化、試験体系の簡素化、試験の一部免除の拡充等公認会計士試験制度の見直し等、所要の措置を講ずることとする。
一 総則
1. 公認会計士の使命及び職責
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする旨の使命規定、及び公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない旨の職責規定を設けることとする。
(第1条及び第1条の2関係)
2. 公認会計士の資格
(1)公認会計士試験に合格した者等であって、業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、実務補習が修了し内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有することとする。
(2)新試験制度の導入に伴い、会計士補の資格を廃止することとする。
(第3条関係)
二 公認会計士試験等
1. 新試験制度の導入
公認会計士試験を短答式試験と論文式試験による一段階二回の試験とすることとする。
(第5条関係)
2. 公認会計士試験の試験科目
(1)短答式試験は、以下に掲げる科目について行うこととする。
○財務会計論(簿記・財務諸表論等)
○管理会計論(原価計算等)
○監査論
○企業法(商法等)
(2)論文式試験は、以下に掲げる科目について行うこととする。
○会計学(財務会計論及び管理会計論)
○監査論
○企業法
○租税法(法人税法等)
○選択科目(経営学、経済学、民法又は統計学のうち一科目)
(第8条関係)
3. 短答式試験科目の一部免除
(1)学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令に定めるものを授与された者に対しては、政令で定める科目を免除することとする。
(2)税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者等に対しては財務会計論を、短答式試験の科目に関連する事務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者に対しては、政令で定める科目を免除することとする。
(3)短答式試験の合格者に対しては、合格発表後二年間のうちに行われる短答式試験を免除することとする。
(第9条関係)
4. 論文式試験科目の一部免除
(1)税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者には租税法の科目を免除すること等とする。
(2)科目合格制を採用し、受験した科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、当該科目の試験を合格発表の日から二年間免除することとする。
(第10条関係)
5. 業務補助等
業務補助等の期間は、公認会計士試験の前後を問わないこととするとともに、現行の第三次試験の受験要件から、公認会計士の登録のための要件とすることとする。
(第3条及び第15条関係)
6. 実務補習
(1)実務補習は、内閣総理大臣の認定を受けた実務補習団体等において行い、実務補習の内容、方法等が基準に照らし適当でないときは、内閣総理大臣が必要な指示をすることができることとする。
(2)実務補習団体等は、その受講者がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告するものとし、内閣総理大臣は、報告に基づき、受講者について、実務補習の修了の確認を行うこととする。
(第16条関係)
三 公認会計士の義務及び責任
1. 大会社等に係る業務の制限の特例
(1)公認会計士が、商法特例法監査対象会社(一定規模未満のものは除く。)、証券取引法監査対象会社等(以下「大会社等」という。)から内閣府令で定める非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等に対して監査証明業務を行うことを禁止することとする。
(第24条の2関係)
(2)公認会計士が、七会計期間以内の政令で定める期間継続して同一の大会社等に対して監査関連業務を行った場合には、政令で定める会計期間、当該大会社等に対して監査関連業務を行うことを禁止することとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合において、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでないこととする。
(第24条の3関係)
(3)公認会計士は、大会社等に対する監査証明業務を行うときは、他の公認会計士等と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用しなければならないこととする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでないこととする。
(第24条の4関係)
2. 研修の受講
公認会計士は、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとすることとする。
(第28条関係)
3. 公認会計士の就職の制限
公認会計士は、会社等に対して監査証明業務を行った会計期間の翌会計期間終了までの間は、当該会社等の役員等に就いてはならないこととする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでないこととする。
(第28条の2関係)
4. 公認会計士に対する指示・処分
内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、必要な指示ができることとする。内閣総理大臣は、公認会計士が当該指示に従わないときは懲戒の処分をすることができることとする。
(第31条及び第34条の2関係)
四 監査法人
1. 監査法人の設立等の認可制から届出制への変更
監査法人の設立、解散、合併及び定款変更の手続を認可制から届出制へ変更することとする。
(第34条の7、旧第34条の8、第34条の10、第34条の18及び第34条の19関係)
2. 指定社員制度の導入
(1)監査法人は、特定の証明について、業務を担当する社員を指定することができることとする。
(2)指定された証明(以下「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負うとともに、監査法人を代表することとする。
(3)指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなった監査法人の債務をその監査法人の財産をもって完済することができないときは、指定社員のみが無限連帯責任を負うこととする。
(第34条の10の4及び第34条の10の5関係)
3. 特定の事項についての業務の制限
監査法人の関与社員が関与した会社等の役員等に就任した場合には、当該監査法人はその翌会計期間まで当該会社等に対して監査証明業務を行ってはならないこととする。
(第34条の11関係)
4. 大会社等に係る業務の制限の特例
(1)監査法人が、大会社等から内閣府令で定める非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等に対して監査証明業務を行うことを禁止することとする。
(第34条の11の2関係)
(2)監査法人は、七会計期間以内の政令で定める期間継続して同一の大会社等に対して監査関連業務を行った社員に、政令で定める会計期間、当該大会社等に対する監査関連業務を行わせてはならないこととする。
(第34条の11の3関係)
5. 監査法人の関与社員の就職の制限
監査法人の監査証明業務を執行した社員は、会社等に対して監査証明業務を行った会計期間の翌会計期間終了までの間は、当該会社等の役員等に就いてはならないこととする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでないこととする。
(第34条の14の2関係)
6. 規制緩和
広告規制の廃止、監査法人の会計年度の弾力化等を行うこととする。
(旧第28条、旧第34条の13及び第34条の15関係)
7. 監査法人に対する指示・処分
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査証明業務の運営が著しく不当と認められる場合において業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、必要な指示ができることとする。内閣総理大臣は、監査法人が当該指示に従わないときは、戒告等の処分ができることとする。
(第34条の21関係)
五 公認会計士・監査審査会
1. 設置
公認会計士審査会の名称を「公認会計士・監査審査会」に改めることとする。
(第35条関係)
2. 会長及び委員の職権の行使、任命等
(1)公認会計士・監査審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行うこととする。
(2)公認会計士・監査審査会は会長及び委員九名以内で組織され、会長を常勤とし、委員のうち一名を常勤とすることができることとする。
(3)会長及び委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとする。
(4)会長及び委員の任期は三年とすることとする。
(5)会長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合等を除いて、その意に反して罷免されることはないこととする。
(6)守秘義務、政治活動の禁止、兼業禁止等、会長及び委員の服務について定めることとする。
(第35条の2~第37条の6関係)
3. 公認会計士・監査審査会に事務局を設置することその他所要の規定を整備することとする。
(第41条関係)
4. 公認会計士・監査審査会は、公認会計士等、監査法人及び日本公認会計士協会に対する検査の結果に基づき、これらの者の監査証明業務又は事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分等を内閣総理大臣に勧告できることとする。
(第41条の2関係)
六 日本公認会計士協会
1. 監査又は証明の業務の調査
日本公認会計士協会は、会員が行う監査証明業務の状況の調査を行うとともに、その調査の結果を定期的に、又は必要に応じて内閣総理大臣に報告することとする。
(第46条の9の2関係)
2. 監督上の命令
内閣総理大臣は、日本公認会計士協会が法令等に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、日本公認会計士協会が必要な措置をすることを怠った場合において、日本公認会計士協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができることとする。
(第46条の12の2関係)
3. 役員の解任命令の廃止
内閣総理大臣が日本公認会計士協会の役員の解任を命ずることができるとの規定を廃止することとする。
(第46条の13関係)
七 雑則
1. 報告及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査証明業務に関し、公認会計士、監査法人等に対し立入検査ができることとする。
(第49条の3関係)
2. 権限の委任
内閣総理大臣は、公認会計士等、監査法人及び日本公認会計士協会等に対する検査等の権限を公認会計士・監査審査会に委任することとする。
(第49条の4関係)
八 罰則
無資格者の監査証明業務等に関して、所要の罰則規定の整備を行うこととする。
(第50条~第55条の2関係)
九 その他
1. 施行期日
この法律は平成16年4月1日から施行することとする。ただし、上記一2及び二については、平成18年1月1日から施行することとする。
2. 経過措置等
その他所要の経過措置を規定することとする。

 検索
検索