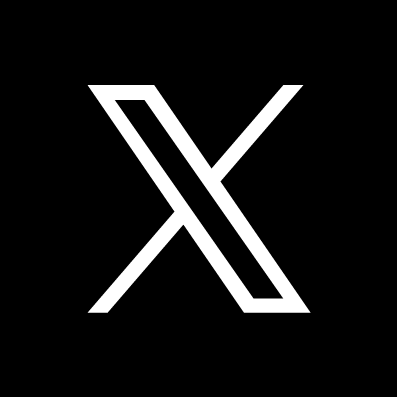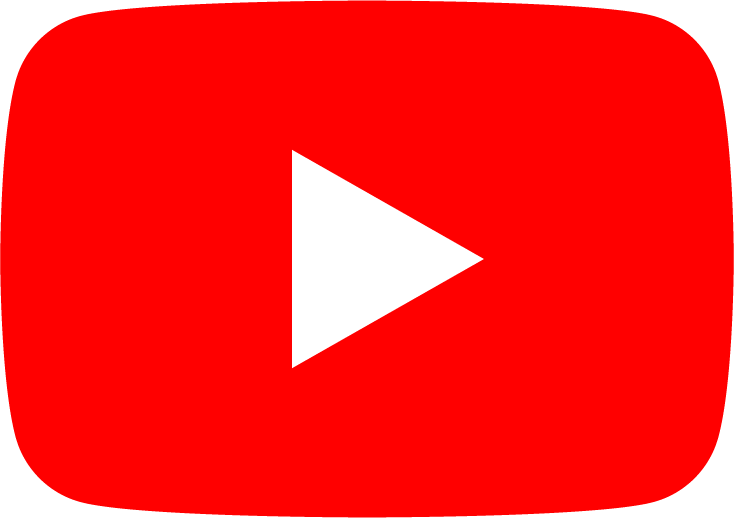評定制度研究会(第1回)議事要旨
1.日時
平成17年1月26日(水)13時00分~14時20分
2.場所
中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室
3.議題
○メンバーの紹介
○研究会の今後の進め方
○事務局説明
○その他
4.議事内容
○冒頭、検査局長より「評定制度研究会」を設立した背景等についての説明があった。
○メンバー等の紹介が行われた。
○岩原 紳作(いわはら しんさく)座長の指名により、野村 修也(のむら しゅうや)委員が座長代理に就任した。
○事務局より、研究会の今後の進め方についての説明があった。
○事務局より、配布資料に沿って、考えられる論点等及び金融検査の概要についての説明があった。
【自由討議での主な意見等】
(評定制度について)
金融制度は、産業や経済の発展に伴って成長発展してきているものであり、我が国の金融制度全体にかかわる問題として、評定制度については我が国の金融制度にフィットする形で導入するための議論が必要。
評定制度の設計にあたっては、特にディスクローズの対象となる様な財務数値等に重点をおいた評定とすべき。
評定基準を開示すれば、金融機関に対する努力目標となり、利用者の利便性の向上にも繋がる制度となるのではないか。
「金融改革プログラム」の趣旨をしっかりとこの制度の中に活かすためにも、市場の参加者が「規制強化」や「行政機能の拡大」というように捉えることなく、ポジティブにこの制度を活用するための手立てについての議論が必要。
「金融改革プログラム」にも盛り込まれている地域再生等の地域経済への貢献をどのように扱うか、検討する必要がある。
「金融改革プログラム」にも盛り込まれている金融コングロマリット、「貯蓄から投資へ」を踏まえた評定制度を考えるべきではないか。
「金融改革プログラム」は、金融庁全体が様々な施策を通じて目指すべき目標であって、評定制度だけですべてが実現できるわけではないし、検査においてその施策の浸透状況をすべて検証できるわけでもない。
システミックリスクを負っている預金取扱い金融機関は、依然としてコンプライアンスとリスク管理の観点は重要であり、財務状況は悪いが顧客満足度が高い金融機関が、高い評価を得ることはあり得ず、このことからすると従来の目線から変ることはあまりないのではないか。
検査については、金融機関に対する監督とは違った役割を担っており、その役割に相応しい検査の運用と評定制度の実現を目指すべきである。
仮に、評定制度が導入された場合に評定結果に対して金融機関側に異議がある場合の意見申し出の方法について、検討する必要がある。
(評定項目について)
米国では「CAMELS」に加えてITとしての「I」も重要になっている。システム・リスクに関する問題についても検討対象とする必要がある。
従来の格付けにおいては、財務の健全性が重要な事項とされていたが、今後の評定制度においては、どのような金融機関に高い点数が付くのか、といった評定の軸足に対する検討が重要。
(評定制度の運用等について)
検査にあたっては、金融機関のリスク特性に応じたリスク管理態勢ができているかを検証すべきであり、杓子定規なものとならないようにする必要がある。
金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の趣旨を踏まえ、債務者の経営実態をきめ細かく検証するよう努めることが重要。
現在、検査が実施されている金融機関名が公表されているが、評定制度を導入した場合には、検査頻度が高いと評定が悪い金融機関ではないか、との一段の風評リスクを招くこととなり細心の注意が必要。
ルールの明確化の観点から、金融庁が実施している金融検査と日本銀行が実施している考査との間で重複感のないようにできないか。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
検査局総務課 瀬戸口(内線2575)、横山(内線2576)、木村(内線2517)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

 検索
検索